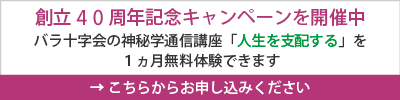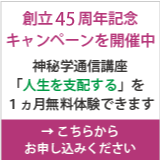自我は死後も生き続けるか
ラルフ・M・ルイス、F.R.C.
これは、恐らく、意見を述べることの最もむずかしい主題の一つであろう。唯一つ確かなことは、たとえどのような立場をとろうとも、必ず論争が起こるであろうということである。この論題の内容は宗教的教義と極めて密接に関連していることから、刺激を与えないようにどのように発言したとしても、少しでも反対の立場にある側からの発言は、誰かの宗教的信念に触れて不快にすることになろう。
恐らく、宗教が発達した最大の要因となったのは、不死への願望であったろう。自己保存本能は、生命力自体の一部分であるから、基本的なものである。つまり、平均的人間にとって、自我の意識と生命の意識とは同じことを意味するのである。人が無意識になっている時でさえ、自我は再び自らを表現しようとして意識のカーテンのすぐ背後で待っていると推定できるのである。初期の人間の思考の何らかの記録が入手できる場合、それらは人が人間の本質の二元性を認めていたことを示している。一方には、物理的知覚の肉体身体自体があり、もう一方には、夢の中で経験された無形の自我があった。
原始人にとって、この無形の自我は、生命力とも関連していたのであり、その生命力は最もしばしば空気と関連していたのであった。息は空気である。死んだ身体は息をしない。したがって、息が立ち去る時、自我もまた、そよ風の翼に乗って運び去られるに違いない。それがギリシア人がソールと息(pneuma)を結びつけた理由である。このプネウマは息と空気に相当する言葉である。また、他の様々の言語の同義語の言葉が、いくつかの初期の宗教の教義の中で同じ意味に使われている。
原始人は体験によって肉体身体の転化を知った。肉体がはかなく腐敗していくことはあまりに明らかであった。しかし空気は消滅されない。人間のまわりの全域には、物質に影響を与えるどのような力にも影響されない、目に見えない空気が存在している。息、空気、生命と非常に密接な関係がある自我すなわち内部の人間もまた、空気と同じように目に見えない。それならば、それも死の原因になるものにも影響されないにちがいない。つまり、原始人は、自我は死後も生き残るという結論に達したのである。このことは、同時に死に対する本能的恐怖を和らげるのに役立った。特にこの観念は人間の生き続けたいという隠れた願望を満足させたのである。
死は転化すなわち一つの表現の形態から別の表現の形態への変遷でしかなくなった。人間は人間として、別の世界で生き続けると考えられた。多くの古代宗教は、生き残った自我は身体を持ち続けるという観念を提示している。自我は完全に抽象的なものではなく、形があり、地上にいた時とほぼ同じ姿に見え、また地上でとほぼ同じような日常生活を行っていると思われていた。この信念のために、エジプト人やエトリアル人やクレタ人のような初期の文化の人々は、死者と一緒に様々の愛好していた所持品を埋葬した。次の人生で死者が彼の宝石や道具や武器、家具さえも、使うと思われていたのである。
来世
この世での物質的形態の中における自我の存在を元に、永遠の生命における自我の存在を類推したのと同じように、古代人は様々な体験と体験との間の類推も行なっていた。このような推理過程の結果、来世での人間はそれぞれ自分自身を認識している、つまり、彼のアイデンティティ(自己同一性)は失われないと推論することが論理的であるように思えたのである。更に、彼は人生の自分の経験全てについての完全な記憶を持ち続ける。そして、一緒にあの世にいる全ての親類や友人と話したり、一緒にいたりすることも自由なのである。このような最も完全なる来世を望むこの気持ちの中には、当然のこと、地上に残っている人々~愛する人々も敵対する人々も~と観念や情報を容易に取りかわすことができるということも含んでいたものと思われる。
心理的には、人間は自分自身の理想の世界を創造しようとしていたのである。彼は自分の愛する人々が自分の世界に住んでいるようにし、そしてその中にはこの世の人間的欲望と願望を満たす様々の物や状態を設定したのだった。来世の世界はこの世の状態と快楽とを移転したものになっていたが、しかし、如何なる苛立ちも制限も限界もないものとなっていた。こうしてあの世は、自分に最も好ましいと人間が考えたことに従って、したい事は何でも出来る場所になったのである。次の人生についてのこの概念では、次の存在はそれが与えてくれる幸福という点ではこの人生を超越しているものになり、死というものは単なる連続する存在の中の瞬間的な中断でしかないものになったのである。
人間は痛み、悪、苦しみ、否定、個人的力のあらゆる制限を端的にこの地上だけのものにしてしまっていたことに注目するのは興味深いことである。地上世界と肉体身体自体とは制限しているのである~事実、初期のギリシア人が考えていたように、肉体はソールの牢獄なのである。ソールあるいはソールと同一視されていた自我が身体から去る時、そのような邪魔者は全て脱ぎ捨てられると考えられていた。
固執される信念
これらの初期の思索家達は、彼らが死後の世界に期待した快楽のほとんど全ては、肉体的で心理的なもの~彼らが脱ぎ捨てていた身体に関連したもの~であることに決して気づかなかったようである。身体を残していくということは苦しみをおいて行くことを意味するだけでなく、当然のこと人間の喜びや感情、快楽への欲望、友人や親類との親しみ、あらゆる官能的満足の全部をおいていくことをも意味している筈である。自我が空気そのもののような霊妙なものであると考えられていた時でさえ、これらを信じる人々は、自我が、肉体と脳とからなる自我の属性と機能を持っていることを期待していたのである。彼らは、人間がよく知っているような熱望や愛そして人間の肉体的精神が考えついた多くの理想への関心が存在すると主張していた。
この種の思考は生き残り本能と密接に関連している。大部分の人間にとって、生命とは力やエネルギーや抽象的な宇宙現象ではなく、むしろそれは主として生きている状態のことである。この生きている状態は、我々がこの存在でよく知っている諸経験を基盤としている。その場合、死後も生き残るということは、生命あるいは一種の意識の連続というだけでなく、我々が良く知っている、生きているという状態の大部分をも同時に意味することになる。
我々のこの発達した文明と宗教の時代の中の大部分の人々は、これらと同じ観念を執拗に抱きしめている。彼らはそのような信念に強く固執しており、どのようなものであっても他の概念的観点から不死を説明しようとすることは彼らの永遠の安全を攻撃するものになるようである。実際にはこのように信じている人々には、神の御国は心の中にある、というバイブルの言葉が最もよく当てはまる筈なのである。しかし、彼らの自我がそのような彼等の概念に満足を見い出していて、深い安らぎを享受しているのならば、たとえ彼らの信念が他人にとって如何にありそうにないものに思えたとしても、彼らの平静は決してかき乱されるべきではないだろう。同時にその反対に、彼らの信念は別の考え方をする人々の概念を抑止する理由であってはならないのである。
人は精神の作用をより多く理解し、実在に関する、より深い哲学的、神秘学的洞察を得るようになると、死後も生き続けることについてのその人の概念は変わっていく。そのような人はもはや、自我は次の人生においてもこの人生と同一の諸体験を得るという観念を信じたり、それに満足を見い出したりはしなくなる。更に、彼は、人格という意味での自我は、我々がこの肉体的存在の中で知っている自我と同じになるという観念を受け入れることもできなくなるのである。
真の神秘家は、自我はある構成要素の枠の中に閉じ込められていることを知っている。一般に表現されている人格であり、我々が認識している自我となっているものは、意識の様々は発現のほんの一面でしかない。一般に理解されている自我は、意志の知覚~つまり、我々の選択力を認識すること~と、我々が外界から受け取る知覚とが合体したものである。つまり、それは現象世界と、そして我々が自分の有機的傾向と好みとを他の全てのものから区別して見分けることの出来るその能力との両方を同時に意識することからなっている。従って、自我は実在を自分と自分でないものとに区別することによって発現している。自我は意識から、すなわち生命力がその有機体と環境とに対してもっている感受性から、生じるのであるから、感受性の変遷または意識の本質の変化は、自我の中味の本質に影響を与える。意識は広大な流れのようなものであり、エゴの認識、つまり意識がそれ自体に対して持っている意識は、この流れの中に深く進行するにつれて変化するのである。
自我は存在し得なくなるのか?
我々が最もよく知っている自我は、我々の選択力としての意志と、外界の知覚とを区別することから生じると先程言ってきた。我々が意識の流れのより深い部分にさらに移行する時、我々は外界の知覚を完全に失ってしまう。更に、我々はもはや外側の世界のイメージを思い出す記憶力の機能さえも示さなくなるものである。
では、このことは、意志の対象となる外界の知覚がもはや残っていないことになるところから、自我は存在し得なくなるということを意味するのだろうか。いや、二元性はまだ存在するのであるが、しかし、それは別の性格のものになっているのである。意志の自我は、たとえば、分裂再生する生きた細胞のように、新しい要素に分割するのである。意志や欲求は意識からはぎ取られてしまっている。何故なら、欲求するものが何も存在しないからである。官能的体験はなくなっている。その結果として、自我の以前の発現のそれぞれに対する次のより上位の領域との関係は、丁度外界に対する我々がエゴと呼んでいるものとのと同じようなものになる。このようにして、自我は普通の自我とは全く似ても似つかなくなるまでに、ますます崇高なものになっていくのである。
宇宙意識
神秘学では個々の人間は、客観的領域と主観的領域においてのみよりもむしろ上記のこれらのより深遠な意識の領域において自我を表現させようと努力しているのである。「宇宙意識」とは「普遍的意識」を認識することである。そのような認識に到達するのも自我ではあるが、それは我々が普通意識している自我の面ではない。その意識の状態では、自我から、世界の全ての有限の特質すなわち形態、寸法、欲望がはぎ取られている。
「宇宙意識」を体験した神秘家や神秘学の学徒は、普通それを法悦、至高の快楽(sublime pleasure)という言葉で言いあらわす。しかし、「快楽」という言葉は誤った表現である。それはすなはち官能的なまたは情動的な快楽ではあり得ない。それは説明困難な状態である。それは沈着の状態に似ていると言うのがそれを最もよく表すであろう。つまり、それはどのような明確な本質も持たないが、同時に全ての感覚から開放されていて、それ自体一様の経験をもたらす。あるいはまた、アナロジーを使用するとそれは、無とか何かの欠如であると言うのに似ている。無は、そこにあったかもしれないが今はそこにない何かを対象にしない限り形容不可能なのである。
もし「宇宙意識」がそのような崇高な意識を生じさせることができるのならば、転化または死の後にも生き残る自我は、この崇高な状態よりは低い本質のものであると仮定されるべきだろうか。確かに、死後も生き続けることができる自我は意識の最も高位の面である筈である。「死後に生命が存在し得る」という前提の全ては、自然には、変化を経てはいるが本質的には不変のままである所の普遍的力が存在するという基礎の上に成り立っている。我々は、生命力は宇宙の普遍的力の特質の一つであると信じている~また我々はこの信念の証明となるものを多く持っている。我々が物質と呼んでいるものを作っているもう一つの力とこの生命力とが結合する時、生命と意識とを持つ有機体が生まれる奇跡あるいは現象が発生する。この有機体が発達すると共に、意識は一層複雑なものになり、その結果、人間の自己認識が発生するのである。
ここでその理由を説明する余白はないが~宇宙エネルギーの全スペクトルつまり鍵盤と関連している「普遍的意識」というものが存在しているのであり、また存在していなくてはならないのである。人間有機体の転化と共に、生命力とその本質の意識は、元々その一部分となっている「普遍的意識」の中に開放される。それは海に落ちる雨のしずくのように吸収されてしまうのだろうか。それとも、人間有機体も中にあった時の、ある種の個性を持ち続けるようになり、小川の水の上に浮かぶ一点の油滴のようになるのだろうか? 神秘家はこの後者の見解をとって、意識にはわずかな改変が起こり、その性格は人格として死後の「宇宙」内に存続されるとしている。
より深遠な思索家は、この「宇宙」の中での存在こそが自我であるとしてはいるが、我々が地上の存在で知っている、そして大部分の宗教家達が信じたがる、人間の機能や知覚のようなものをこの自我に与えることはしていない。何故に、我々がこの地上で経験すると同じ愛着の理想や同じ幸福の基準が「宇宙」内に存在するということに固執しなければならないのだろうか。ローマの哲学者セネカは如何にも適切に次のように言った。「死とは何か。それは悲劇の仮面だ。それをまわして調べてみよ。ほら、噛みつきはしまい。哀れな肉体は遅かれ早かれ、以前にそれとは別々になっていたように、もう一度霊から引き離されなければならないのだ。」
「だから哀れな肉体よ、汝のしばしの期間を従順に通過して自然に戻り、満足して汝の旅を終えよ~丁度、オリーブの実が熟した時、それを生じさせた自然を祝福し、それを実らせた木に感謝して、落ちてしまうように。」
雑誌「バラのこころ」1986 No.2より
![]()
もしあなたが、宗教とは別のところに、
人生の根本的な疑問に対する答え、重要な選択や判断を誤らずに行なう方法、心と体の癒し、宇宙意識に達する道をお探しであれば、下記のキャンペーンにお申し込みください
バラ十字会の神秘学通信講座「人生を支配する」の1ヵ月分の教材と、季刊雑誌「バラのこころ」を無料でお届けさせていただきます。